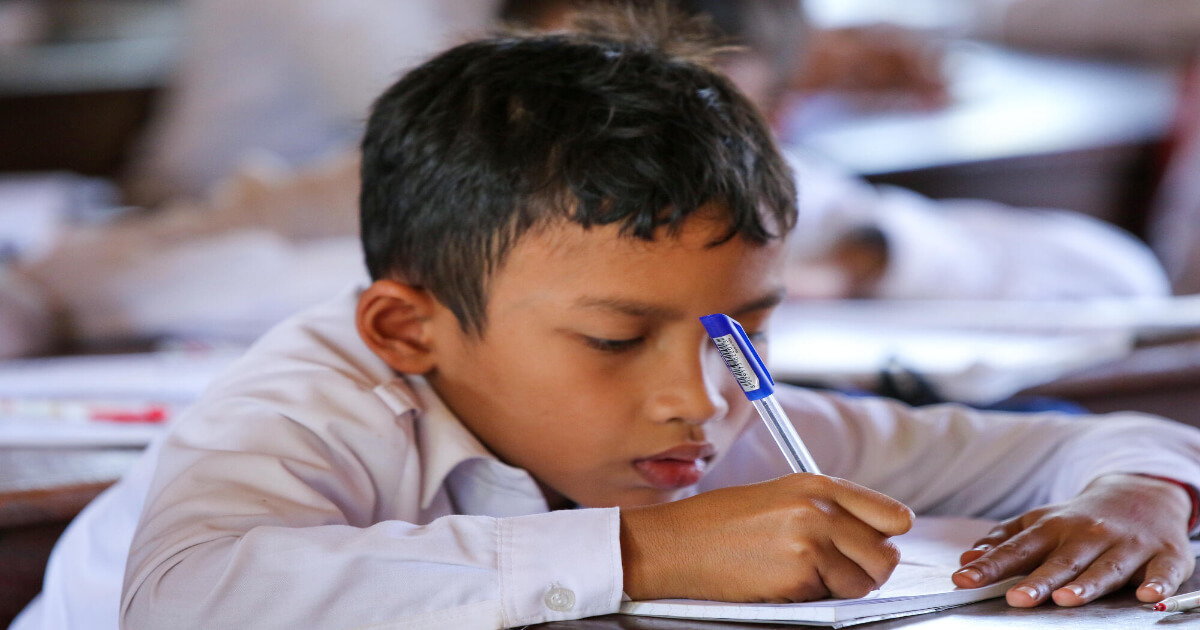エクアドルの教育の現状と問題【データを用いて分かりやすく解説】
- 教育
- #エクアドル
- #中南米
- #教育
この記事でわかること
エクアドルの教育にはまだまだ課題も多く、その背景には貧困や民族格差などさまざまな社会問題が影響を与えています。この記事では、エクアドルの教育制度や現状、問題点について分かりやすく丁寧に解説します。
エクアドル共和国(以下、エクアドル)は、南アメリカ大陸の北西部、赤道直下に位置する国で、コロンビア、ペルーと接しています。国土の中央にはアンデス山脈が縦断しているため標高が高く、首都キトの標高は2,800m。白人と先住民の混血(メスティーソ)が国民全体の8割弱を占め、公用語はスペイン語、宗教はキリスト教(カトリック)が主流です。
エクアドルの教育にはまだまだ課題も多く、その背景には貧困や民族格差などさまざまな社会問題が影響を与えています。この記事では、エクアドルの教育制度や現状、問題点について分かりやすく丁寧に解説します。
エクアドルの教育の現状と問題

まずは、エクアドルの教育制度や教育の現状、同国が抱える教育の問題点について解説します。
エクアドルの教育制度
エクアドルは、10-3-4制の教育制度を導入しており、基礎教育が10年、中等教育が3年、大学などの高等教育が4年という制度となっています(注1)。
基礎教育では、児童は基礎学校に5歳になる年に入学し、1~10年生まで学習します。日本の小学校と中学校にあたる教育期間であり、この10年間を義務教育としています。
中等教育は、3年間学習します。日本の高等学校にあたり、一般教育課程と技術教育課程に分かれています。各課程修了時受け取れる中等教育修了証が、大学などの高等教育への進学条件となります。
またエクアドルでは、基礎教育と中等教育を合わせた13年間が義務教育として定められている点も特徴の一つと言えます。
高等教育では、大学だけでなく、教員養成校や芸術教育校、技術者養成等を行う高等専門教育機関などがあります。
データから見る教育の現状
次に、データを基にエクアドルの教育の現状について見ていきましょう。以下で、UNESCO(国際連合教育科学文化機関)(注2)と世界銀行(注3)、USAID(アメリカ合衆国国際開発庁)(注4)が発表しているデータをもとに解説します。
| 小学校の純就学率(2018年) | 90.9% |
| 小学校の第1学年への純入学率(2018年) | 66.1% |
| 小学校の最終学年までの継続率(2017年) | 98.6% |
| 小学校の未就学児童の割合(2018年) | 1.3% |
| 小学校の留年率(2020年) | 0.3% |
| 小学校の教員訓練を受けた教員の割合(2007年) | 71.6% |
| 小学校の教育訓練を受けた教員1人当たりの児童数(2007年) | 31.5人 |
- 小学校の純就学率は、小学校で学習すべき5~14歳の児童の全人口に対し、実際に小学校に在籍している児童数の割合を表したものです。
- 小学校の第1学年への純入学率は、小学校に入学するべき年齢である5歳児の全人口に対して、実際に新規で入学した児童数の割合を表したものです。
- 小学校の最終学年までの継続率は、小学校の第1学年に入学した児童のうち、最終的に初等教育の最終学年に到達した児童の割合を表したものです。
- 小学校の未就学児童の割合は、本来小学校に通うべき年齢の児童のうち、小学校に就学していない児童の割合を表したものです。
- 小学校の留年率は、全児童数に対して、2年以上連続して同じ学年に留まっている児童数の割合を表したものです。
- 教員訓練を受けた教員の割合とは、国が定める教員として必要な最低限の組織的な教員訓練(現職前または現職後)を受けた小学校教員の割合を表したものです。
- 小学校の教育訓練を受けた教員1人当たりの児童数は、全国の小学校の児童数を上述の訓練を受けた教員数で割った比率を表したものです。つまり、1人の訓練を受けた教員で、約31.5人の児童を指導している計算になります。
エクアドルの教育の問題点
以上のデータより、エクアドルの教育の問題点は次のようにまとめられます。
●小学校に通うべき年齢(5~14歳)で通えない児童がまだまだ多い
●小学校の入学年齢である5歳の時点で小学校に入学できない児童がまだまだ多い
●全教員に対して教育訓練を受けた教員の人数の割合が十分ではない
国連が掲げる持続可能な開発目標(SDGs)の目標4「質の高い教育をみんなに」の中には、「2030年までに、全ての子どもが男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする」というターゲットがあります。
この達成のためには、まず就学率の改善が急務となります。90.9%という数字は、一見高いように感じますが、教育は全ての児童が等しく受けるようになるべきです。したがって、10人に1人の児童が小学校に通えていない現状は問題であり、限りなく100%に近い状況を目指す必要があります。
また学校に入学させるだけでなく、質の高い教育を誰もが等しく受けることも重要です。そのためには、教員の質の向上が必要です。
このような問題には、どのような背景が潜んでいるのでしょうか。問題を解決するためには、問題の裏に潜む様々な社会課題や現状を知る必要があります。
エクアドルの教育問題の背景

ここまで、エクアドルの教育の現状と問題点について解説しました。次に、エクアドルの教育問題についてより深く理解するために、その原因や背景を見ていきましょう。
貧困による問題
エクアドルが抱える問題の一つに貧困があります。エクアドルは2021年10月現在、国連の指定する後発開発途上国(LDC)のカテゴリには分類されていませんが、世界銀行によって高中所得国(UMICs:Upper Middle Income Countries)に分類されています(注5)。上位中所得国とは、2016年時点の国民一人当たりの国民総所得は3,956米ドル以上12,235米ドル以下の国・地域のことを指します。
エクアドル国内における貧困は改善傾向にあるものの、まだまだ貧困は問題であり、世界銀行が貧困ラインとして基準を定めた1日1.9米ドル以下で生活している貧困層の人々は、国民の約3.6%の割合を占めています。また、エクアドルが定める貧困ライン(1日あたり約5.5米ドル以下)で暮らす人々は、人口の約25%を占めています(注3)。
貧困が原因で教育に与える負の影響の1つに、児童労働があげられます。児童労働とは、最も本来学校に通うべき年齢の児童のうち、市場で働いて賃金を得たり、親の仕事や農業仕事を手伝うことで自営業に従事したり、または、料理、洗濯や兄弟の世話などの家庭内労働に従事している児童のことを指します。
アメリカが2020年に行った調査によると、エクアドルの5歳から14歳までの児童のうち、労働に従事している児童の数は全体の約8.2%で302,796人におよぶというデータが明らかになっています(注6)。2020年のパンデミックの影響で状況はさらに悪化していることが予想されます。
2002年に行われた研究(注7)では、労働を行っている児童の約34.4%が、1日当たり平均で5時間以上働いており、約3%は、10時間以上働いているというデータも示されています。
児童労働は、その労働時間が長ければ長いほど、学校へ行く時間がなくなり、結果として児童の学習の機会を阻害することになります。そのため、貧困の撲滅が急務なのです。
地域・民族格差による問題
また、地域や民族の格差もエクアドルの教育に影響を与えています。
例えば、上述した児童労働の数についても都市部と農村部で人数を比較すると、農村部在住の男子児童が最も労働活動に従事している比率が高く、その次に農村部在住の女子児童、都市部に在住する男子児童と続きます(注7)。
つまり、都市部と農村部で所得の格差がある可能性が高く、農村部の児童の小学校への就学率や入学率なども、都市部に比べて低い可能性がきわめて高いと考えられます。
また、農村部に住む人々の中には先住民族も多くいます。エクアドルには20以上の先住民族がおり、そのうち約9割はケチュア族と呼ばれる民族です。
1998年の調査(Borja-Vega and Lunde 2007)では、高地農村地域に住む先住民族の98%が貧困層であるという結果が出ました。先住民族のほとんどは、就業して所得を得る機会が乏しいという現状にあります。農村地域に住む先住民族の76%は「低技能労働者」と見なされています。そのうち賃金労働者は26%で、74%は非賃金労働(自営と家族就業者)です(注8)。
したがって、先住民族の人々は貧困層が多く、児童労働などによって教育へのアクセスが困難であるという課題に直面し続けているのです。
ワールド・ビジョンの取り組み
私たちワールド・ビジョンでは世界の子どもたちが教育を受けられるよう、開発途上国の教育や学校の支援活動を行っています。
エクアドルでの取り組み
ワールド・ビジョン・ジャパンは、エクアドルでの支援活動を2007年から現在に至るまで続けています。特に生計向上や教育の質、子どもの栄養状態、保健・衛生状況の改善を目指して複数の地域で活動を行っています。その一部を紹介します。
プンガラ地域開発プログラム
首都キトから南へ約240km、車で約4時間の場所に位置する、チンボラソ県リオバンバ郡プンガラ町は、標高3,000m以上の山岳地帯で、先住民が住民の9割を占め、スペイン語以外にケチュア語も使用されています。貧富の格差が大きいエクアドルの中でも特に貧しい地域で、電気、上下水道、教育・保健施設などのインフラ整備が遅れています。貧困に加え、薬物・アルコール依存や家庭内暴力なども問題となっています。このような課題を解決するために、次のような支援活動を行っています。
- 生計向上のために、クイ(食用モルモット)の飼育・繁殖による収入向上の支援や養鶏や乳製品の加工に関する研修の実施
- 教育の質向上のために、学校の備品の提供や教員への教材作成や教授法に関する研修の実施、住民への子どもの権利や教育の重要性に関する啓発活動の実施
- 子どもの栄養状態の改善のために、子どもの健康管理、病気の予防、栄養に関する保護者への研修実施、家庭菜園での栽培支援、栄養バランスのとれた食事の調理法に関する研修や乳幼児の定期的な身体測定の実施
- 衛生知識の向上のために、手洗いや爪切りなど衛生的な習慣についての啓発と、衛生用品の提供、薬草を使った伝統的な治療法の普及活動の実施
コルタ地域開発プログラム
首都キトから南へ約210km、車で約4時間の場所に位置する、チンボラソ県コルタ郡は、標高3,000m以上の山岳地帯で、先住民が住民の9割を占め、スペイン語以外にケチュア語も使用されています。貧富の格差が大きいエクアドルの中でも特に貧しい地域で、インフラ整備の遅れや家庭の経済的困窮に加え、衛生環境の改善や教育の質の向上が課題となっています。このような課題を解決するために、次のような支援活動を行っています。
- 生計向上のために、クイ(食用モルモット)の飼育・繁殖による収入向上の支援や、酪農を行う家庭への牧草の種の提供
- 教育の質向上のために、学校の備品の提供や教員への教材作成や教授法に関する研修の実施、住民への子どもの権利や教育の重要性に関する啓発活動の実施
- 子どもの栄養状態の改善のために、栄養バランスのとれた食事の調理法に関する研修やビタミン剤や粉ミルクを提供
- 衛生知識の向上のために、手洗いや爪切りなど衛生的な習慣についての啓発や、安全な水の使用方法(煮沸消毒等)に関する研修の実施
チャイルド・スポンサーシップ
チャイルド・スポンサーシップとは、ワールド・ビジョンを代表する取り組みの1つで、開発途上国の子どもと支援者の絆を大切にした地域開発支援です。支援者の皆さまからの月々4,500円の継続支援により、上述したエクアドルにおける活動を行っています。
チャイルド・スポンサーになっていただいた方には、支援地域に住む子ども「チャイルド」をご紹介します。ご支援金はチャイルドやその家族に直接手渡すものではなく、子どもを取り巻く環境を改善する長期的な支援活動に使わせていただきます(エクアドルの子どもたちの様子)。
チャイルド・スポンサーシップは、エクアドルだけでなく、アジア・アフリカ・中南米など世界21カ国に支援を届けており(2020年度実績)、子どもの健やかな成長のために必要な環境を整え、支援を受けた子どもたちが、いずれ地域の担い手となり、支援の成果を維持・発展させていくことを目指しています。
今すぐチャイルド・スポンサーシップに参加するには

公式ホームページにてチャイルド・スポンサーシップ参加のお手続きを承っています。支援内容についての詳細や個人情報等を入力していただくだけで、簡単に申し込むことができます。
また、ワールド・ビジョンでは、世界のさまざまな問題やそれらに対する取り組みをまとめた資料をご用意しています。皆さま一人ひとりが世界の問題や現状を「知るため」のきっかけとして、ご活用いただけます。詳しくは、「伝える・広める」をご覧ください。
ワールド・ビジョンでは皆さまのご支援・ご協力をお待ちしています。
今あなたにできること、一日あたり150円で子どもたちに希望を。
SHARE
この記事が気に入ったらシェアをお願いします